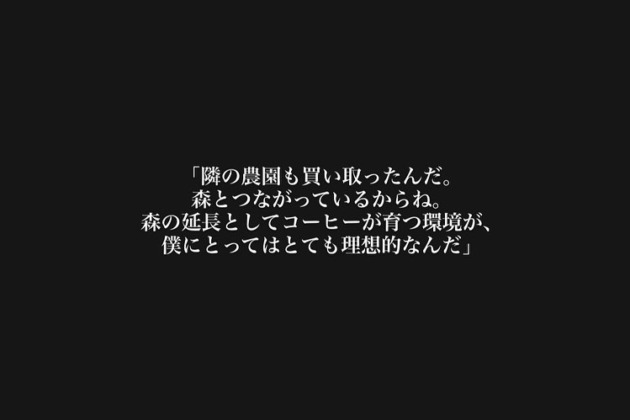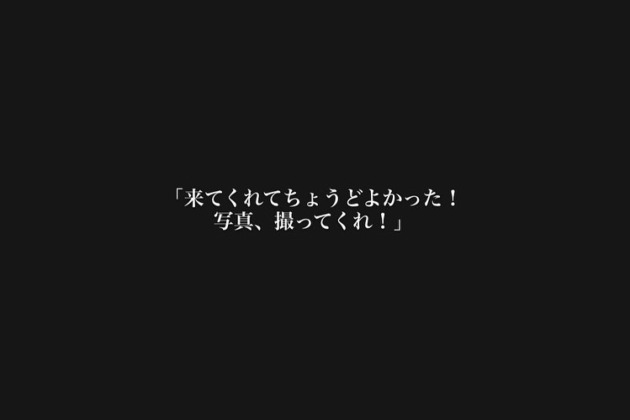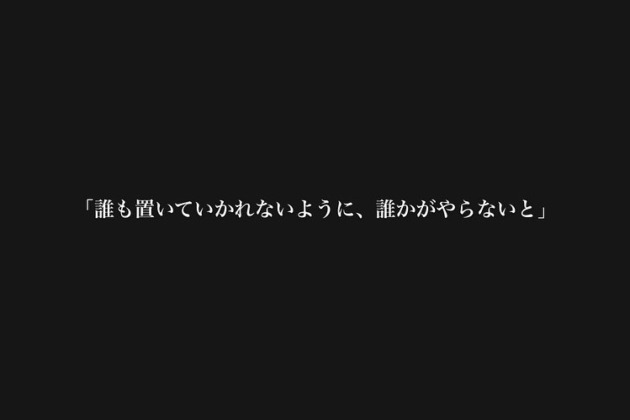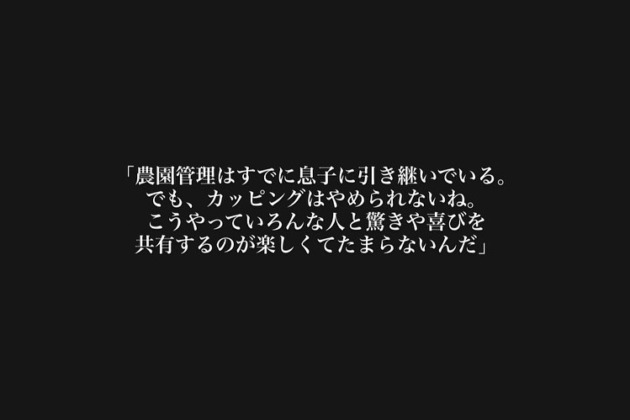イトログ_019

『スペシャルティコーヒー』
今年で中米を訪問するのは8回目。すっかり毎年の恒例になってしまった。
当時から会っているコーヒー農家さんたち、新しく知り合ったコーヒー農家さんたち、そしてその家族。
その農園で働く労働者たちや、毎年滞在するホテルのスタッフさんたち、たくさんの友人や知り合いが増えた。おかげで日本にいるときよりも慌ただしい毎日を過ごしているかもしれない。
お付き合いしている作り手たち全員がスペシャルティコーヒーを作るために情熱を注いでいる。そこには僕たち消費国のプロたちの協力が不可欠であることもこの8年間で体感として実感している。
正直に言うと、僕はここ数年スペシャルティコーヒーという言葉を控えてきた。
スペシャルティコーヒーという言葉が、単に美味しいコーヒーを指す言葉、そして販売側の売り文句のように使われ始めたのに嫌気がさしたからだ。
少なくとも僕がスペシャルティコーヒーに出会ったころはこうではなかった。
スペシャルティコーヒーを提供するその意識が生産国の作り手にまできちんと行き届いたお店が多かった。一杯一杯が感動的で本当に美味しかった。だからこそ当時は消費者だった僕もその世界に強く惹かれた。
お店を立ち上げてしばらくして、スペシャルティコーヒーという言葉が市民権を得ていくのに比例するようにスペシャルティコーヒーを提供するお店が増えた。
その過程でこの言葉が、単に美味しいコーヒー、そして高品質を謳う売り文句的に乱雑に使われ、消費者に間違ったように理解されていくのがとても腹立たしかった。
今年、ニカラグアでは例年の半分ほどの収穫しかできていない。
度重なる雨、嵐のような暴風、そして経済が招いた労働者不足。収穫を待つコーヒーたちを横目になかなか進まない収穫作業、その間に降る雨と風が実を落としてしまう。
品質こそ良かったものの、国からのなんのサポートもない農家さんたちからすると収穫量が収入に直結している。
これまでもこういったことがなかったわけではない。肥料の値段が一気に上がったこともあったし内戦や治安の関係でコーヒーが作れないこともあった。サビ病という病気が蔓延したときには農家は自費でその対応に追われた。8年前から毎年会っていたサラティエルさんは労働者を探している途中に事故で亡くなった。
しかし消費の現場ではそんなことはほとんど感じさせない。コーヒー屋は自店のスペシャルティコーヒーの品質を高らかに謳い、生産国のそれを消費者に伝える人はほとんどいない。
現地に行くことだけが正しいとは決して思わないけれど、せめてそういったことが起きていることを知ろうともしないことがとても怖く思えている。
スペシャルティコーヒーの理念のその素晴らしさは、美味しさの恩恵が生産国の作り手にまできちんと還元されることにある。
素晴らしい自然環境や、そこに生きるたくさんの名もなき作り手たちの情熱的な仕事の結果にこの美味しさが誕生したことを、飲んだ人に伝え、考え、行動してもらう。
そうやってこの美味しいコーヒーをいつまでも、いつの世にも楽しめる環境を整えていくことにスペシャルティコーヒーという言葉の真髄があると僕は思っている。
飲み手が美味しければそれで完結するのではない。このコーヒーには続きがあるのだ。
それがこのコーヒーのテーマでもある「From seed to cup(種からカップまで)」という言葉に集約されている。
いつしかトレンドワードのように扱われ拡がっていく様子が心底嫌になって僕はスペシャルティコーヒーという言葉を使わなくなった。
でもやっぱり黙ってはいられなくなった。今のこの街のコーヒーシーンを見ても、このままだと確実にこの素晴らしい美味しさを持ったコーヒーがいつの日かなくなる確信がある。商業的に別の言葉に置き換わり、いつしかその本来の理念は失われていくのが見えている。
もう一度、僕は、僕自身がコーヒーの世界に入るきっかけになったこの言葉を使おうと思っている。
スペシャルティコーヒーの本当の美味しさ、そしてその理念の素晴らしさをきちんと伝え、賛同してくれる人たちと一緒に考え、話し、微力な行動をおこそうと思っている。
僕たちのお店は、スペシャルティコーヒーの専門店だ。